- 無線LANにおけるチャネルの基礎
- チャネルボンディングについて
無線LANのことはだいたいわかる1冊です。
辞書的に手元に置いておくと便利です!
チャネルとは
無線LANはアクセスポイントとクライアント端末(PCやスマホなど)のデータの送受信は電波を介してやりとりします。
この時に重要になってくる要素の1つがチャネルです。
チャネルとは周波数の幅のことを指し、データの送受信を行うアクセスポイントとクライアント端末は同じチャネルを使用する必要があります。
しかし、近くにいるアクセスポイントが同じチャネルを使用すると干渉を起こしてしまい、速度低下などの不具合が生じてしまいます。
そのため、近くのアクセスポイントとは異なるチャネルを使用するよう設定が必要になります。
2.4GHz帯のチャネル
まず、2.4GHz帯のチャネルを見てみます。
| チャネル | 中心周波数 |
|---|---|
| 1 | 2,412 MHz |
| 2 | 2,417 MHz |
| 3 | 2,422 MHz |
| 4 | 2,427 MHz |
| 5 | 2,432 MHz |
| 6 | 2,437 MHz |
| 7 | 2,442 MHz |
| 8 | 2,447 MHz |
| 9 | 2,452 MHz |
| 10 | 2,457 MHz |
| 11 | 2,462 MHz |
| 12 | 2,467 MHz |
| 13 | 2,472 MHz |
| 14 | 2,484 MHz |
2.4GHz帯のチャネルを使用する無線の規格で現在主流なのは802.11ax、802.11n、802.11gです。14chが使用できるのは802.11bという規格までなので、現在使用できるチャネルは1-13chまでとなります。(※一部製品を除く)
前述の通り、隣り合うAPが同じチャネルで電波を出力すると電波干渉が起き、速度低下などの問題が発生します。
また各チャネルは中心周波数が5MHz離れており、中心周波数から±11MHzを使用(帯域幅)して通信を行うことが上記表よりわかります。
つまり、隣り合うAPはこの利用幅の重複を避けなくてはいけません。
よって同時に使用できるチャネルとしては、「1・6・11・(※14)」、「2・7・12」、「3・8・13」の3パターンとなります。
5GHz帯のチャネル
5GHz帯もチャネルの一覧を見てみましょう。
| チャネル | タイプ | 中心周波数 | 屋外利用可否 |
|---|---|---|---|
| 36 | W52 | 5,180 MHz | 条件付きで可 |
| 40 | W52 | 5,200 MHz | 条件付きで可 |
| 44 | W52 | 5,220 MHz | 条件付きで可 |
| 48 | W52 | 5,240 MHz | 条件付きで可 |
| 52 | W53 | 5,260 MHz | 不可 |
| 56 | W53 | 5,280 MHz | 不可 |
| 60 | W53 | 5,300 MHz | 不可 |
| 64 | W53 | 5,320 MHz | 不可 |
| 100 | W56 | 5,500 MHz | 可 |
| 104 | W56 | 5,520 MHz | 可 |
| 108 | W56 | 5,540 MHz | 可 |
| 112 | W56 | 5,560 MHz | 可 |
| 116 | W56 | 5,580 MHz | 可 |
| 120 | W56 | 5,600 MHz | 可 |
| 124 | W56 | 5,620 MHz | 可 |
| 128 | W56 | 5,640 MHz | 可 |
| 132 | W56 | 5,660 MHz | 可 |
| 136 | W56 | 5,680 MHz | 可 |
| 140 | W56 | 5,700 MHz | 可 |
| 144 | W56 | 5,710 MHz | 可 |
上記の表より、5GHz帯は全部で20チャネル使用できることがわかります。
※144chは2019年7月に新規で追加
また、それぞれのチャネルは屋外利用の可否、また後述するDFS機能の有無によってW52、W53、W56とタイプ分けされています。
5GHz帯は使用帯域幅が20MHzのため(中心周波数から±10MHz)、チャンネル間で周波数の重なりがありません。
よって、どのチャネルを使用しても電波干渉しないため、2.4GHz帯のように使用するチャネルの制限を受けません。
DFS(Dynamic Frequency Selection)
無線LANで利用する特定のチャネルは気象レーダーなどでも使用しており、アクセスポイントなどがそれらのレーダー波を検知すると電波を止める機能をDFSと言います。(レーダー波に優先的利用権があるため)
DFS機能は搭載が義務付けられており、主要メーカのAPであれば基本搭載されています。
DFS機能が動作する周波数帯は5GHz帯のW53、W56だけですので、W52に限定して使用していればDFSによる影響は受けません。
DFSの具体的な動作は以下のようになっています。
- レーダー波等を検知し干渉していた場合、即時にチャネルを切り替える。切り替え後のチャネルが干渉していないか1分間検査するため、1分間無線LANが使えない状態となる。
- 干渉していたチャネルは30分間利用停止となる。
チャネルボンディング
チャネルボンディングとは、チャネルを複数同時に使用し利用周波数帯域幅を大きくすることです。
帯域幅が大きくなるとデータ通信を高速化することができます。
例えば、5GHz帯は1チャネル20MHzの帯域幅ですが、隣り合うチャネル同士(例えば36と40)を束ねて40MHzとして使用することができます。
使用するWi-Fi規格にもよりますが、同時に4つのチャネルを束ねて80MHz、8つのチャネルを束ねて160MHzで使用することもできます。
2.4GHz帯のチャネルボンディングも可能ですが、元々干渉せずに同時に使用できるチャネルが最大4つのため、チャネルボンディングした場合2つとなってしまいます。
そのため、メリットよりデメリットが大きいので通常は使用しません。
チャネルボンディングによる通信速度の向上幅は、規格によって若干の差がありますが理論上帯域数が2倍になれば通信速度も約2倍になります。
まとめ
今回は無線LANでのチャネルについて解説しました。
日本では現在2.4GHz帯と5GHz帯を使用することができます。
どちらの帯域も電波干渉が起こらないよう使用するチャネルを選ぶ必要があります。
またDFSといって、気象レーダなどのレーダ派が使用する帯域と5GHz帯の帯域が一致する箇所があり、レーダ派に優先使用権があるため使用チャネルを変更しいないといけないと制限もあります。
DFSが発動すると一定時間無線LANが使えないため、設計時に考慮しましょう。
チャネルボンディングは使用する複数のチャネルをまとめて1つのチャネルとして使用する技術です。
無線規格によって若干の差はありますが、使用する周波数帯域が2倍になれば通信速度も2倍となります。
デメリットとしては同時に使用できるチャネル数が減少するため、一般的にチャネルが豊富にある5GHz帯のみでの使用となります。
その他無線LANに関して解説しているのでぜひご覧ください!
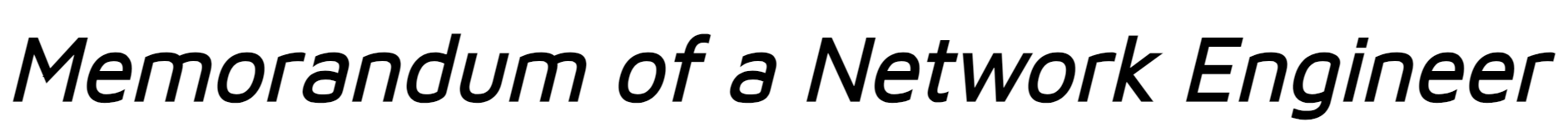
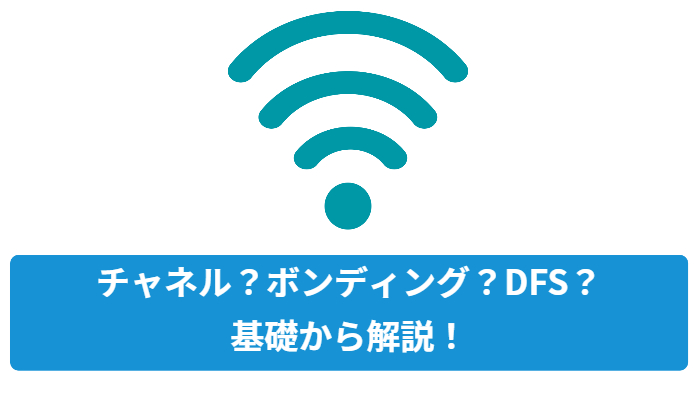


コメント